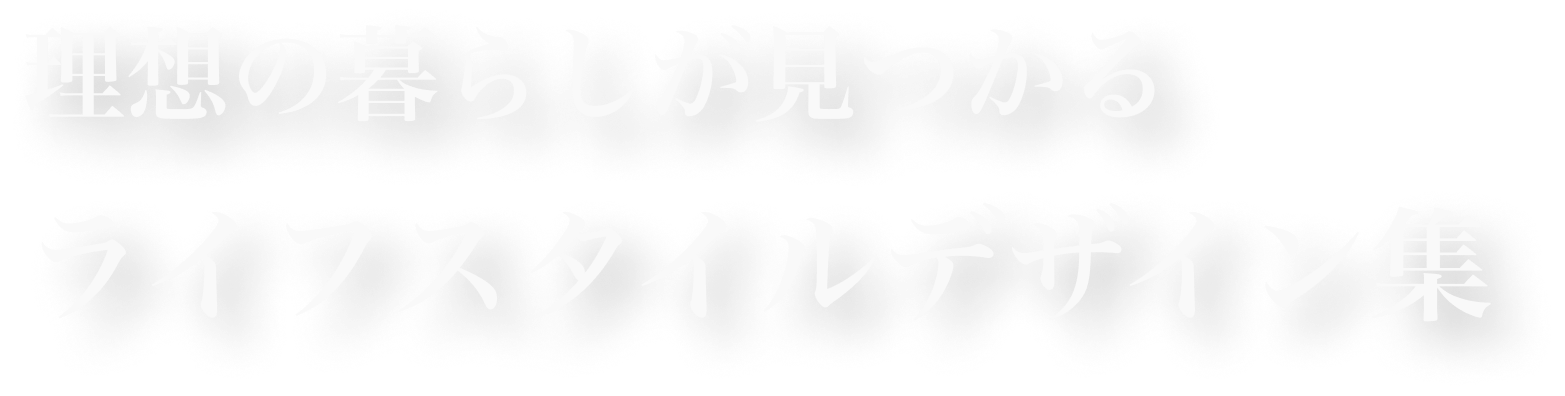この記事を読んでいるあなたは、
「吹抜けの家のデメリットを知りたい」
「吹抜けの家にする際のポイントを知りたい」
と思っていないでしょうか。
本記事では、実際に吹抜けの家に住んでいる方の口コミをもとに、吹抜けの家のデメリットや住む際の注意点を紹介しています。
吹抜けの家を建てた後に、
「吹抜けの家を建てなきゃよかった」
と後悔しないためにも、吹抜けの家に実際に住んでいる方の評判を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

経験者が語る吹抜けの家の5つのデメリット
ここでは、実際に吹抜けの家に住まれている、もしくは住んだことのある方の口コミをもとにデメリットを紹介します。デメリットとして以下、5つが挙げられます。
- デメリット①:空間が広く光熱費が高騰
- デメリット②:音や匂いが広がりやすい
- デメリット③:耐震性が下がる可能性がある
- デメリット④:2階の部屋が狭くなる
- デメリット⑤:メンテナンスが大変
それぞれ詳しく解説します。
デメリット①:空間が広く光熱費が高騰
賃貸に住んでる今でも、吹抜けの電気代の高さにおののいているのだけど、これ一戸建ての吹抜けになったら、一体どこまで上がるの??吹抜け憧れるけど、でも、光熱費…!
引用元:Twitter(@totemama_)
吹抜けが光熱費を高くするというのは、一般的には事実です。吹抜けからの自然光の入りやすさや、広がりのある開放感は、建物全体の明るさを確保しやすくする反面、暖気が上昇しやすい構造になっているため、暖房費が高くなる可能性があります。
また、夏場には吹抜けからの熱が屋内にこもりやすく、冷房費がかかることもあります。ただし、最近の住宅は高断熱・高気密化が進んでいるため、光熱費の面での問題は解決されている場合もあります。
しかし、光熱費は建物の構造だけでなく、使用する機器や設備、住民の生活習慣によっても変わってきます。したがって、吹抜けのある家で光熱費を抑えるには、断熱性能の高い窓や壁、エアコンや暖房器具の選び方、省エネライフスタイルの実践などが必要です。
デメリット②:音や匂いが広がりやすい
家を建てて6年、焼肉は室内でしないと誓いそれを守ってる!(庭でBBQ風にして食べる) でも外って天候に左右されるし地味にめんどいし、室内焼肉を解禁すべきか… 吹抜けなんで2階まで焼肉の匂いがつくと嫌なんだよね でも焼肉もっと気軽に食べたい…
引用元:Twitter(@nonpaka)
上記の口コミに関しては、吹抜けのデメリットとは直接関係がないと言えます。
室内での焼肉に関しては、室内の換気対策や空気清浄機の導入などで匂いの対策が可能です。ただし、吹抜けがある場合、煙や匂いが上に上がってしまうため、上階に匂いが移る可能性があることは考慮すべきです。
そのため、室内での調理に関しては、十分な換気対策を行う必要があります。
デメリット③:耐震性が下がる可能性がある
【性能】 断熱、気密、耐震が家の性能の3大指標と自分は思ってる。 3つをそこそこの数値にするのはいける。 ただ、間取りや意匠性を保ちながらというのが難しい。 特に耐震性。 大開口や吹抜けにすると構造的に弱くなるし。 その辺を両立できる設計者探しが難易度S
引用元:Twitter(@PichanHappyLife)
上記の口コミの主張は、一定の根拠があると言えます。建物の耐震性能は、建物の安全性を左右する非常に重要な要素です。
一般的に、建物の耐震性能は壁や柱、梁などの構造体の強度によって保たれます。吹抜けは、大きな開口部があるために、構造的には弱くなると言われています。そのため、吹抜けがある場合には十分な補強が必要となります。
ただし、現代の建築技術では、吹抜けを設けながらも、十分な耐震性能を確保することが可能です。
デメリット④:2階の部屋が狭くなる
庭は広いかな…庭だけは周りの景観さえ良かったら撮影に使えそうなくらい綺麗にはしてる…家の中はダイニングが吹抜けだから2階狭い。私の部屋めちゃめちゃ狭い💢💢💢
引用元:Twitter(@cloudywolf666)
上記の口コミには、吹抜けによって2階のスペースが狭く感じるというデメリットが示唆されています。
一般的に、吹抜けはダイニングスペースやリビングスペースを広々とした印象にする効果がある一方で、2階の部屋が狭く感じることがあります。
また、吹抜けからの音や匂いが2階に伝わることもあり、それが部屋の狭さを感じさせる原因となることがあります。吹抜けを設ける場合は、このような点にも注意して設計を行う必要があります。
デメリット⑤:メンテナンスが大変
毎年の事ですが年末の吹抜けの窓掃除…ハシゴを使ってやるんですよね💦明かり取りには良いのですが掃除の事も考えて間取りは決めたらいいと感じるカッパです😂とは言え自分で間取り考えたので文句言えないのですが😭
引用元:Twitter(@takeshi_jiyujin)
上記の口コミにあるように、吹抜けは高い場所に窓があるため、窓や天井の掃除が手間や危険を伴うことがあります。
また、窓掃除に必要な道具や脚立、ハシゴの保管場所にも注意が必要です。吹抜けのある住宅を設計する場合には、掃除やメンテナンスがしやすいように考慮する必要があります。
例えば、天井に埋め込んだ照明器具や可動式の天井パネルを設置することで、掃除が容易になる可能性があります。
吹抜けを取り入れる際の3つのポイント
ここからは吹抜けを取り入れる際の、以下3つのポイントを見ていきましょう。
- 住宅性能
- 空調設備
- 間取り
一つずつ見ていきましょう。
住宅性能
吹抜けの家を建てる際に住宅性能を重視すべき理由は、吹抜けによって発生する空気の流れが住宅の断熱性や換気性能に影響を与えるためです。
吹抜けによって室内の空気が上昇するため、床や壁からの熱損失が大きくなり、エネルギー効率が悪化します。
また、吹抜けの上の部屋の換気が悪い場合には、不快な空気がたまり、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
したがって、吹抜けを設置する際には、住宅性能を考慮し、適切な対策を講じることが重要です。
空調設備
吹抜けは、室内の温度や湿度が変化しやすくなるため、適切な空調設備を導入することが重要です。
吹抜けによって上部が暖かく、下部が冷えてしまうことがあるため、空気の循環を促進する換気設備や、床暖房や完全に独立したエアコンなどの温度調整設備が有効です。
適切な空調設備を導入することで、吹抜け内の空気の循環や温度調整を行い、快適な住環境を実現することができます。
また、適切な空調設備を導入することで、室内の温度や湿度を一定に保つことができるため、健康面にも配慮することができます。
吹抜けを設置する際には、空調設備による室内環境の維持を重視し、適切な設備を導入することが大切です。
間取り
吹抜けの家を建てる際に、間取りを重視する理由は、吹抜けが部屋全体の空間の印象を左右するためです。
吹抜けは、開放感や高級感を演出することができますが、間取りによっては、逆に狭く感じたり、不自然な配置になってしまったりすることがあります。
適切な間取りを設計することで、吹抜けの高さや位置、周囲の部屋とのバランスを考慮することができます。
吹抜けがあることで生じる開放感や高級感を活かしたインテリアの配置やライティングも重要なポイントです。
間取りやデザインを考慮しながら、吹抜けの設置場所や高さなどを決定することで、快適で高級感のある空間を実現することができます。
吹抜けを取り入れる際には、間取り全体を見渡し、吹抜けを活かしたデザインを取り入れることが大切です。
吹抜けの家を建てるなら浅井良工務店
「和歌山で魅力ある吹抜けの家を実現したい!」と考えている方は浅井良工務店がおすすめです。
浅井良工務店の魅力は、吹抜け住宅に特化した家づくりであることです。注文住宅の約9割が吹抜けのある住宅であることからもわかるように、吹抜けについての知識や技術に優れていると言えます。
上記でお話しした『住宅性能』『空調設備』『間取り』に対してもプロフェッショナルな提案をしてくれるため、まずはお気軽にお問い合わせをしてみるといいでしょう。
興味のある方は以下のボタンから、相談してみてください。
まとめ
今回は吹抜けの家に関する5つのデメリットを見てきました。それは以下5つです。
- デメリット①:空間が広く光熱費が高騰
- デメリット②:音や匂いが広がりやすい
- デメリット③:耐震性が下がる可能性がある
- デメリット④:2階の部屋が狭くなる
- デメリット⑤:メンテナンスが大変
吹抜けの家は広々とした開放的な空間がとてもおしゃれです。誰もが一度は吹抜けの家に憧れるでしょう。メリットだけを家を建てるのではなく、デメリットもしっかりと理解した上で吹抜けの家を検討しましょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。